ユダヤ思想の神秘的文献でカッバラの基礎的体系を含む書に、「ゾハル」(光輝の書)がある。古代アラム語で書かれたといわれる、「ゾハル」は、カバラ神秘思 想のなかでは数少ない価値の高い文献である。「ゾハル」は最古典の聖典である。 ところでカバラとはなんだろうか。正しくはカッバーラー
”Qabba´la´h”といわれ、ユダヤ密教である。カッバーラー ”Qabba´la´h”は、<相伝><口伝>もしくは<伝統>を意味する語で,英語では、Cabala。本質的な意味では、神から<授けられたもの>となる。厳格な参入儀礼を経て資格をもった弟子にだけ教えられ,長い間,秘密の闇に隠されていた。こうした、カバラが非ユダヤ人に知られるようになったのは、13世紀すぎになってからのことである。
カバラは、《エゼキエル書》におけるエゼキエルの幻視を追体験することによって、〈神の玉座もしくは戦車(メルカバ)〉に参入を果たそうとする技法であり、その意味でカッバラとは、純粋な密教のカテゴリーに入る。カバラは、直接〈神〉に近づき,その目前に仕えること,つまり〈臨在〉へのプロセスを教える体系である。カバラの教理、「生命の樹」は、信仰の対象ではなく,認識の対象となっており、ゆえに、メルカバに至る階梯の秘密が「生命の樹」だと言える。今日われわれも目にすることができる「生命の樹」は、密教の汎神論に似た構造をもっており、神秘数を3と10をもって、アルファとオメガを内包させている。
さて、「ゾハル」は、このアラム語という今や滅亡しようとしている言葉で書かれ、西暦2世紀の学者、シメオン・ベン・ヨハイの手になるものと言われる。イエスが年間の布教をなされた期間、庶民に語るときはアラム語を用い、ヘブル語ではなかった。当時庶民が一般に使うアラム語は、現在でも中近東の一部の地方で細々と使われている。よく聞くとアラビア語の抑揚に近いものを感じる。「ゾハル」は、やはり、悟りを目的とした秘密の教えであった。カバラ神秘思想家の到達しようとした境地もまた体験的なものであり、彼らは暝想により「メルカバ」(天の車)に接することに励んだ。
ところで、ヘブライ語で「戦車」の意味をもつ「メルカバ」は神の玉座を意味している。面白いことに、現在のイスラエル軍が実践配備している戦車は「メルカバ」と呼ばれている。メルカバとは極めて具象的な形を暗示し、じつはマンダラを彷彿させるところがある。
「メルカバ」は造形的な要素が濃く表れる。数理的な整合性と秩序をもつものとして科学的な感じさえ与える。どこかサイエンティフィックなのである。
箱崎総一著「カバラ」によると、メルカバの形状の出典としてはエゼキエル書が大きな存在をもっているとする。天の車、メルカバは神の玉座であり、ある形状をもつのであり接神の究極の客体であるという。
「カバラ神秘思想家たちが到達しようとした境地もまた、そこにあった。実践的暝想を通じて、天の車(メルカバ)の幻想(ヴィジョン)を見ることを目指した。その具体的暝想手段はすべて師伝のかたちで口頭で伝えられていたので、文書化された記録は少数の例外を除きほとんど存在していない。」・・・
この戦車という意味を持つ「天の車」とは、一体なんだろう? 天の玉座の象徴であるメルカバとはなにか。光輝の書の冒頭は「天の車」が、少なくとも光り輝くものであることが明確に記されている。
○「光輝の書」序章
「はじめに王が閃光のランプのごとき天の燦然たる輝きの軌道を定めた。そこから流出したものは玄妙不可思議な神秘的な限界なきものであり、白でもなく、黒でもなく、赤でもなく、緑でもなく、いかなる色彩でもない形なき核によってとり囲まれていた。彼は(それらの総ての)手段を講じた際、その内部に色彩を適合させた。
その内部のランプからある種の光輝が流れだし、そこから以下のものには色彩がつくられた。おおい隠された最高の神秘的な力は限界のない裂目のなかにあった。
それはあたかも空虚な裂目が存在しているようであり、天上の、神秘的な点から前方を輝かしていた雷撃の力によって照らしだされるまで、総ては不可知のままに止まっていた。その(天上なる)点を超えればそこはもはや不可知の領域である。そこでその1点は、”原始点”(reshite 始まり)と呼ばれ、この1点より総ては始まり、創造された。
それは、(次のように聖書に)記されている。
”賢いものは、大空の輝きのように輝き、また多くの義に導くものは、星のようになって永遠にいたるでしょう。”ダニエル書12ー3」
天の車すなわちメルカバの表現は旧約聖書には次のように至る所にある。
「主はケルブに乗って飛び、風の翼をもってかけり、闇をおおいとして、自分のまわりに置き、水を含んだ暗き濃き雲をそのまくへきとされました。」詩篇18ー11
「エシュルンよ、神に並ぶものはほかにいない。あなたを助けるために天に乗り、威光をもって空を通られる」申命記33ー26「神をむかって歌え、そのみ名をほめうたえ。雲に乗られる者にむかって歌声をあげよ」 詩篇68ー4
「見よ、主は早い雲に乗って、エジプトに来られる」 イザヤ書19ー1
「見よ、主は火のなかにあらわれてこられる。その車はつむじ風のようだ。激しい怒りをもってその憤りをもらし、火の炎をもって責められる」 イザヤ書66ー15
「主よ、あなたが馬に乗り、勝利の戦車に乗られるとき、あなたは川にむかって怒られるのか」 ハバクク書3ー8
「彼らが進みながら語っていたとき、火の車と火の馬があらわれて、二人を隔てた。そして、エリアはつむじ風に乗って天にのぼった。」 列王紀下2ー11
「彼は霊の車で引き上げられ、(その)名は彼ら(地上の住民)の間から消えた」 エチオピア語エノク書70ー2
「それを乗せた車を風が吹き送り、太陽は没して天から姿を消し・・・」 同書72ー5
「その球は天球のようでそれが乗る車は風に吹き送られ、光が適度に授けられる。」 同書73ー2「栄
光の幻を見しはエゼキエルなり。主これをケルビムの車の上に現出したまえり」 ベン・シラの知恵49ー8
こうして、メルカバに関する抜粋は不可思議さを秘めながらも何か形状をもっていることを推測させる。「雲のような」 「炎のように光る」「霊の車」「火の車」「ケルビム」などであり、客観的に表現されている。このケルブは乗り物に象徴されるときがあるが、蓮華座にお座りになっている如来の意味。蓮華座は宝珠(無数の光の粒)によって成り立っている。
エゼキエルは、無数の眼が、そこにあったとする。これはうろこのように見えただろう。ここに「蛇」が象徴される。メルカバの最も詳しい記述はエゼキエル書の第1章にあり、非常に難解であるが、メルカバのイメージを彷彿とさせるに十分である。
エゼキエル書第1章は圧倒する詳細な接神体験の記述である。メルカバを示差する神秘体験の最高峰といえよう。
カッバラの思想は、メルカバは東洋のマンダラに対応する。とくに、直接、神と合一しようとする秘儀をもっているという意味では、驚くべき類似性をもっている。メルカバを体系的に図式化したものに「生命の樹」には3の数秘展開を示す図版である。
○カバラ秘密結社は、輪廻転生を信じていた
3世紀から6世紀の間に「セーフェル・イェツィーラー」(形成の書)という最も重要なカバラ文献が成立する。「生命の樹」の10のセフィロトと22のパス(小径、こみち)が、はじめて説かれた書である。さらに、12世紀には古典的カバラの原典、「セーフェル・ハ・バーヒール」(清明の書)が現れる。この書は、明確に輪廻転生を説いている。モーッアルトの歌劇、「魔笛」では秘密結社の聖所で輪廻転生が高らかに歌われる幕がある。モーッアルトはフリーメーソンの名で知られる秘密結社に入会していたと今日では考えられている。
13世紀には、モーセス・デ・レオン Moses de Leon(1250‐1305)が「ゾーハル(光輝の書)」を著した。これは2世紀に活躍したラビ,シメオン・ベン・ヨハイの事跡を記しながら、聖書のカバラ的解釈がいかなるものかを示す根本経典である。カバラはユダヤ人への虐殺や追放、暴行の嵐のなかで、根本密教として発達してきた。キリスト教に改宗させられるなど、ユダヤ人のアイデンティティが崩壊の寸前に立ったとき、カバラは必然的に結社の形を取らざるをえなかった。
○カバラの哲学は〈生命の樹〉に集中されている。
それは図のような構造をもった図式で、この〈樹〉は右側の〈力の柱〉と左側の〈形の柱〉および中央の〈均衡の柱〉からなり、上から〈流出界(アツィルト)、〈創造界(ベリアー)、〈形成界(イェツィーラー)、〈活動界(アッシャー)からなる4段階の階梯をもつ複合構造をもっている。
この三本の柱と四つの世界の交錯点に10個のセフィロト
sephirot(数)が配される。この10個の数を通して,創造主たる〈神〉が顕現世界に現れるのである。ピタゴラスによれば、1をアルファとすれば10はオメガとなる。
| aaa | aab | aac | , | 3 |
| bbb | bba | bbc | abc | 4 |
| ccc | cca | ccb | , | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
*10は、九進法では1である。つまり、アルファ=オメガ。(元に戻る)ケテルは〈神〉の最初の顕現、最下の〈マルクト〉は〈神〉の最終的顕現で、1=10となる。従って、10と1は、一つの光球を意味するので、10から1を引いた数、9が光球の数である。
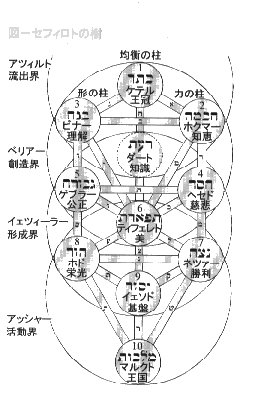
1から10までのセフィロト(光球)はそれぞれ固有の属性をもつ。それは一なる神の位相を表す。1のセフィラー(セフィロトの単数形)はケテル(王冠)、2はホクマー(知恵)、3はビナー(理解)、4はヘセド(慈悲)、5はゲブラー(公正)、6はティフェレト(美)、7はネツァー(勝利)、8はホド(栄光)、9はイェソド(基盤)、10はマルクト(王国)と呼ばれる。ケテルは〈神〉の最初の顕現、最下の〈マルクト〉は〈神〉の最終的顕現で、この2極の間が他の八つのセフィロトによって分節され、〈ケテル〉から〈マルクト〉への〈神〉の流出を示すとともに、〈マルクト〉から〈ケテル〉への〈神〉の上昇を表す。これは、すでに紹介したマンダラの向下門、向上門の教えと同じである。セフィロトの間は22本の小径(こみち)で結ばれている。これには22(21+1)のヘブル語のアルファベット、およびそれが対応する数値が配当され、それぞれの文字と数値が表わす象徴が割り当てられているのである。この図のなかにある色分けできる三角形の数は21個である。ヘブル語のアルファベットはそれぞれの数値が対応しており、文字の組合せである単語または文章も一定の数値をもつことになる。数と文字を暗号のように使うカバラでは、同じ数をもつ単語または文章は置換えが可能であり、それによってさらに深い意味を持たせることができる。たとえば、智恵2=慈悲4=美6、理解3=公正5=勝利7、王冠1=栄光8=基盤9、といったように分類すると、グループの合計はそれぞれ、(3)、(6)、(9)とゲマトリア化することができる。これらの、グループの合計数は、すべて3の倍数で構成される。つまり、セフィロトの樹の、すべての数字の観念が3の倍数で規定されている。また、そうなるように仕組まれている。そうした例は、ほかにも聖書の随所に見つけることができる。ヨハネの黙示録に記されるすべての数字は、3で割り切ることができるのも、秘められた法則によっている。
○始め神は複数だった
創世紀の冒頭には「神」がエロヒム(Elohim)と複数形で書かれ、後にヤハウェ(Yahave~)と単数系に記される。こうした異なった記載のつながりは、多くの学者をさまざまに悩ませてきた。その矛盾は、このセフィロトの樹を見れば、簡単に理解できる。セフィロトの樹には、見てのとおり三つの柱がある。均衡の樹、力の樹、形の樹である。これは、3つの柱が3つの神を示し、三神一体を示している。神が単数であることと、複数であることが矛盾しないのは、三位一体が根底にあるからである。唯一の神とは論理的必然性からいって、それは両性具有であり、たとえば、それを万物の母と言おうと、万物の父と言おうと、すべての源泉は一つの起源にほかならない。
そこで、セフィロトの樹の三つの柱の意味を見てみよう。セフィラ(Sephirah`)から、つまりケテル(keteher)から伸びる均衡の樹は、すべてを統合している。その統合の樹には、さらに二本の樹が副えられている。このことは上の図にある通りである。中央の樹の右は、万物の父であり、アッバ(Abba)の柱である。その意味は「大いなる父」である。左は、万物の母であり、アイマ(Aima)の柱で、意味は「大いなる母」である。アッバとアイマは、男性原理と女性原理を意味する。その中間にある統合の原理から、三つの柱はなりたっている。このことは、われわれの語感ではタオで言う、「陰陽中」と言ったほうがずっと解りやすい。つまり、これは同じ原理なのだ。万物を産み出すには、これら三つの柱、言いかえれば三神が必要であって、最後の10番目セフィラに至って、はじめて、物質世界が産み出される。セフィロトの樹の構図は、10番目のセフィラ「マルクト王国」に至って、物質世界に降りたつ。「マクルト王国」は、万物創造の役割を担っており、母、女王、産婆、さらには花嫁などを意味するシェキナー(Shekinah)とも名づけられている。つまり、根源的な光である王冠ケテルから、物質化された王国(マクルト)まで、男性原理と女性原理と統合原理の3つの柱を跨いで、セフィロトがつづら折りのように配置されているというわけである。
○マンダラとタオ
ユングが傾倒した金丹教の「太乙金華宗旨」は、神仏は黄金の光の本性をもち、黄金のように輝く聖者であると述べている。光を「思う」ことによって、神仏の輝きを「観る」ことを可能ならしめる実践的なテキストである。「太乙金華宗旨」は、止観の一法をプラグマティクにとらえた書であるが、原理的な面もすぐれて高度である。「太乙」とは原初の無上なる偉大な「1」なる「道」(タオ)の元神であるとする。易教では陰陽の変化のない永遠に消滅しない存在で、万物を司るものを「道」という。
「道」の本体は「玄」であり、それが「1」であって、その「1」から「多」が生まれる。つまり、玄は「有」と「無」を内包し(2)、それが、「陰・陽・気」(3)を孕んで万物を生成するとする。
「気」とはエネルギーである。あたかもマトリックス機能を見る思いがする。「有と無」、すなわち「陰」と「陽」とはそのエネルギーの波動の両極であり、万物の表れは「道」の然らしめるものであるので、万象に「理」が表れてくる。この「理」を知る力を「徳」という。「徳」とは、「陰陽」と「気」を知る能力を指す。「理」という言葉は本来の然らしむる姿を言い、それに順応する力を「徳」という。
韓非子は雑念を除くことが、「徳」が盛んになると説く。「徳」は、己れを無にし、精妙なる気を知ることを説く。万物はすべて変化であるが、本来の姿にやがて帰る。これを「常」といい、不滅の存在を認識することを「明」といい、その不滅の運動の現れを知るものを「道理者」という。「タオ」は普遍的に万物に現われているとする。
こう読んでみると、「タオ」はすぐれて科学的ナニュアンスを含んでいる。真理といわれる論理的筋道は概ね宇宙創世の原理を含んでいるように思えてくる。道教は宇宙の成り立ちなど、科学式的な論法を好むような印象を受ける。
「金華はすなわち光なり。光は是れ何色なるや。象(かたち)を金華に取る。また、一光を秘す。」
一光とは「タオ」であり、元神を言う。そのイメージは金華(マンダラ)であるというのだ。この金華とはマンダラに他ならない。中心に、(只中に)光がある。
「光は単に身体の中にあるのでもなければ、単に身体の外にだけあるのでもない。山も河も大地も、また太陽と月が上で輝くのも、すべてはこの光でないものはない。」
万物はすべてこの光によって、存在する、これが、自然のなかに「理」(真理)をみいだす東洋的な英智につながる。
「したがって、光は単に身体の中にだけあるのではない。
理解と明晰さ、洞察と解明、及び、すべての精神の働きは同じようにこの光にほかならない。したがって、それはまた体の外にだけあるものでもない。天地の光の輝きは、あらゆる大きな1つの三千世界をみたしている。これと同じように、個々の体の光の輝きも、天をみたし、地をおおっているのである。したがって、光が回転し始めれば、同時に天も地も、山も河も、すべてのものがそれとともに回転するのである。人間の身体の中にあるすぐれたエッセンスを、上方に向って両眼の間に集中すること、これが、人間の身体の(秘密をひらく)偉大な鍵なのである。そなたたちは、よくこのことについて熟考せよ」。
また、太乙金華宗旨では、実践的技法を説く。
「呂祖師は言われる。回光(止観)という言葉はいつから知られるようになったのであろうか。それは関伊子によって明らかにされたものである。もし回光(止観)をめぐらせば、すべての天と地の諸力は必ず結晶する。これが、微細な思念と呼ばれるものであり、また気の純化されたもの、思考の純化されたものなのである」。
回光(止観)は、単に個々の身体のエッセンスを循環させることではない。それはそのまま、宇宙と形成の真のエネルギーを回転させることなのである。
回光の意味は、すこし難しいがこういう事だ。「回」とは、流れている想念を「止」めることだ。想念を「止」めると、光が「観」える。「止」めることと、「観」ることを同時に行うので、合わせて「止観」という。
「回光」は、すなわち「止観」である。「止観」は万物を覆う光を観照することなのだ。想念を止めることは、その前に「気」を止めることだ。
「気」が動けば、想念も動く。
想念の活動を止めるにはコツがある。それは、「自分の呼吸」をコントロールすることだと言う。「気」は想念のエネルギーなのだから、これを抑えることができれば、無理なく想念が静まる。ようするに、「気」が止まれば、想念も止まる。そこで、想念を直接に抑止することは困難なので、呼吸からコントロールする。「気」が横溢であれば、想念も乱れる。そこで、「調息」が、まず「気」を暴れさせない(制御)ようにする。「調息」が心を平静にするのだ。「気」が外に向かわなければ精神の光が見えてくる。要は、想念(思考)を「止」めるコツなのだ。やがて、精神の光は「縁中」(下丹田=太陽神経叢)に結晶する。下丹田に光が集中すると、光が見えてくる。下丹田に光の(黄金の胎児)意識を繋ぐと、眉間(両目の間)に光が観照できるようになる。光は眉間に、現われているように見えるが、実は下丹田に結晶しているのだ。こうして、実際われわれが外界を見る「目」とは関係がない作動によって観照されるのである。
下丹田に結晶する光が、第三の目(眉間)に投影されている。だから、はじめから眉間で見よう見ようとしては、見ることができない。
こうして、天眼通が生じる。この、光は、すなわち「金華」である。金華とはマンダラだから、そのとき、彼は光と調和しているのだ。こうして、技法は心の動きを止める呼吸法から入る。暝想と呼吸とは表裏一体である。さて、接神論の奥にはそれぞれ呼び方は異なるが共通の、あるイメージ(形)が顕れてくる。それは暝想や祈りのなかに顕れる神仏の真の姿であり、炎のように光り輝くものであり、時に「火」のようで、あたかも太陽のようだ。永遠の存在で、かつ創造のはじまりからある。歴史的にこれらの接神体験がその主体者を超越者にし、宗教を勃興させる。簡単にいえば、溢れる光りの世界との共振であり、それとのコンタクトである。
マンダラが一元であり、かつ無限であるから、マンダラのどこの光を見ているのか、それを知ることは難しいが、中心をもち、その只中の光こそ全一であることを知れば、同時に自分を真に知ることになるだろう。
<第七章完>
![]() HOME-TOPへ
HOME-TOPへ